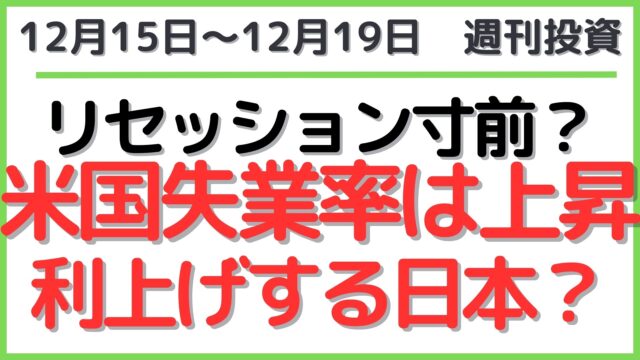 週刊投資経済
週刊投資経済 【日米の経済動向】アメリカ経済はリセッション寸前、日本経済はなぜ利上げ?
2025年12月発表の米雇用統計・CPI、日本CPIの結果を詳報。アメリカの失業率上昇と金利引き下げが示すリセッションの前兆、そして日銀の0.75%への利上げ決定が日本経済に与える影響とは?
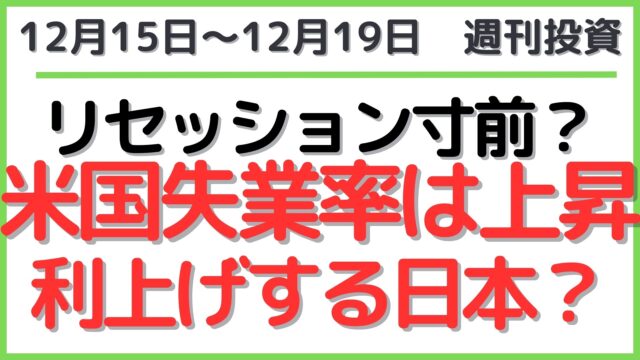 週刊投資経済
週刊投資経済 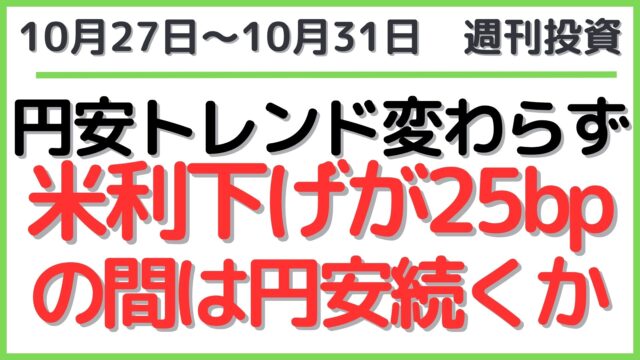 週刊投資経済
週刊投資経済 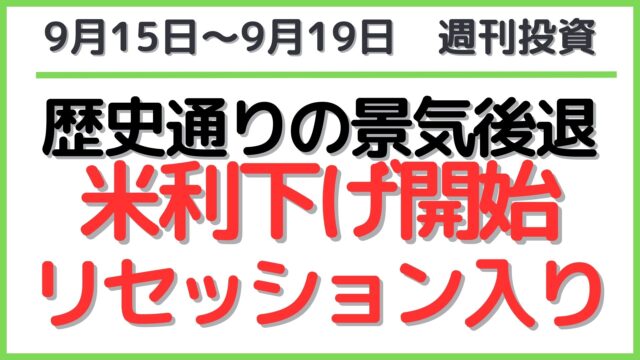 週刊投資経済
週刊投資経済 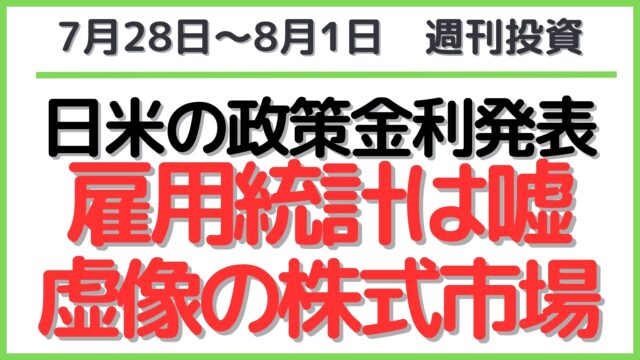 週刊投資経済
週刊投資経済 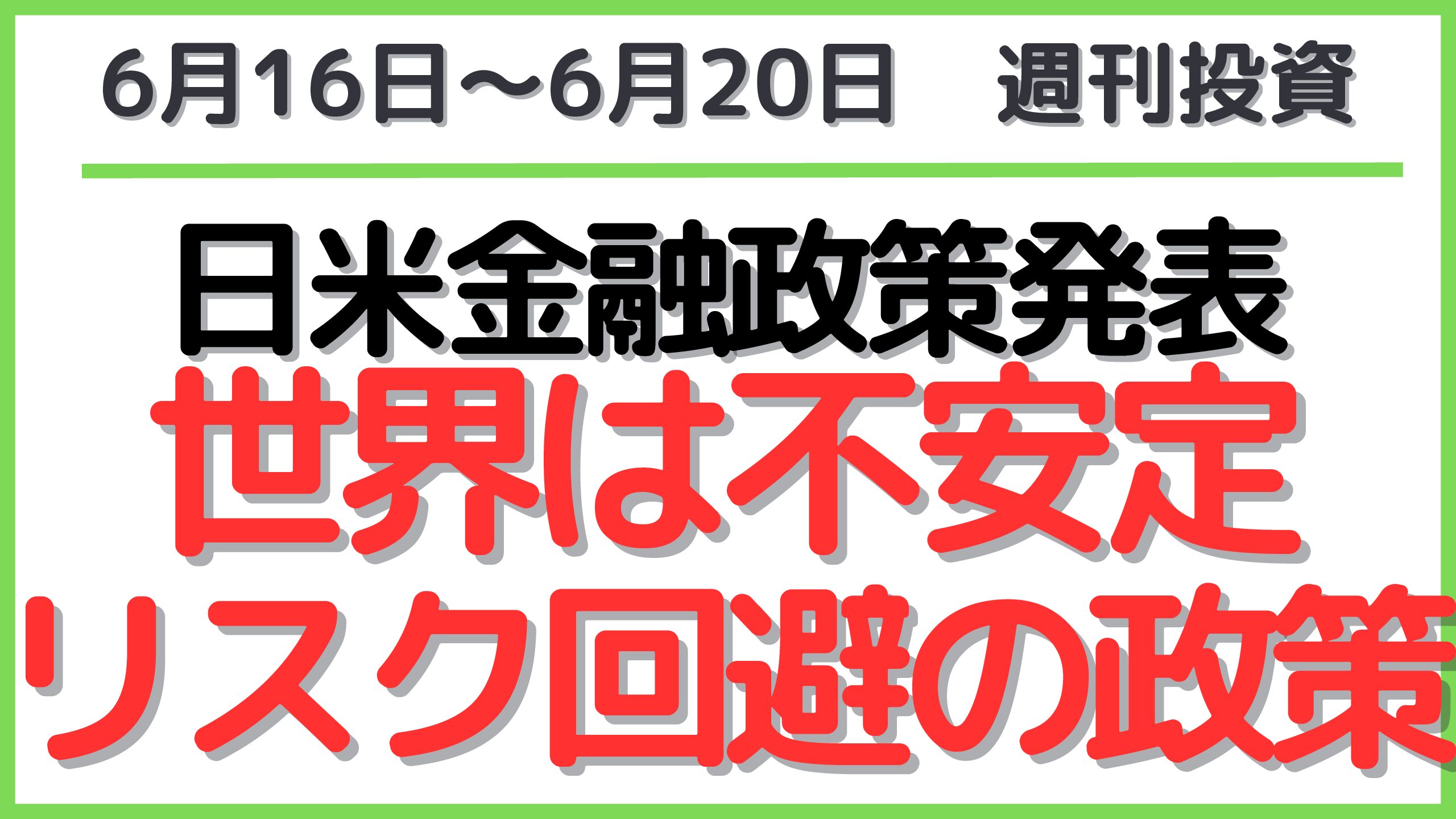 週刊投資経済
週刊投資経済 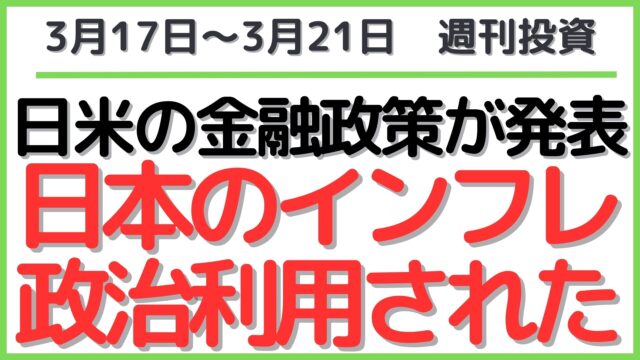 週刊投資経済
週刊投資経済  週刊投資経済
週刊投資経済 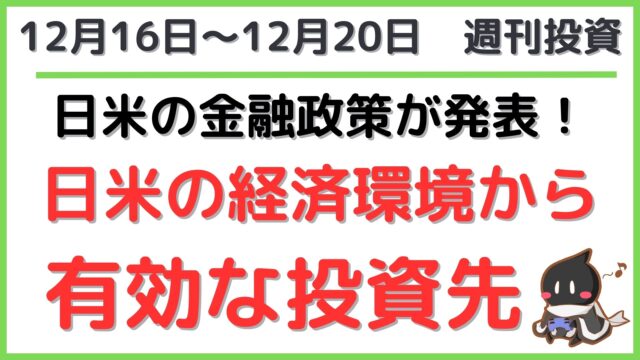 週刊投資経済
週刊投資経済 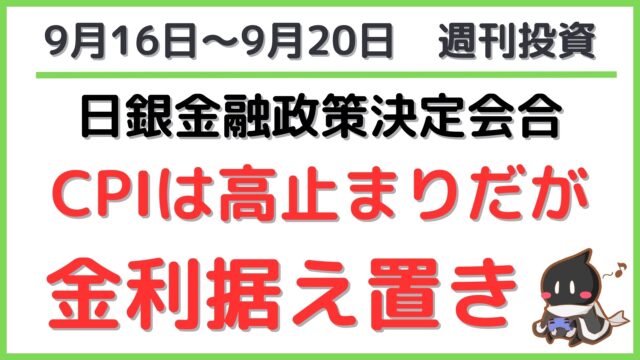 週刊投資経済
週刊投資経済 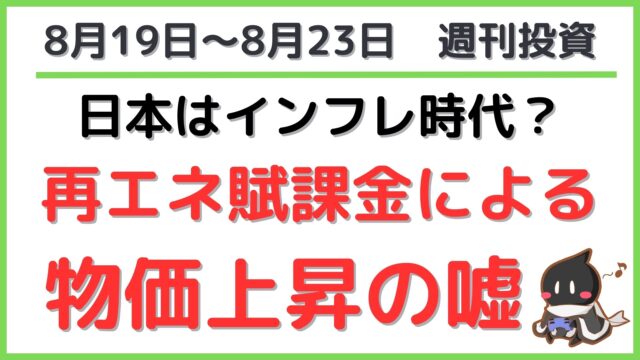 週刊投資経済
週刊投資経済